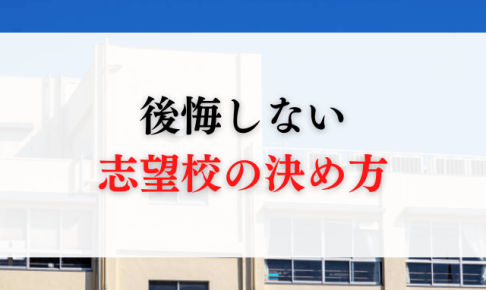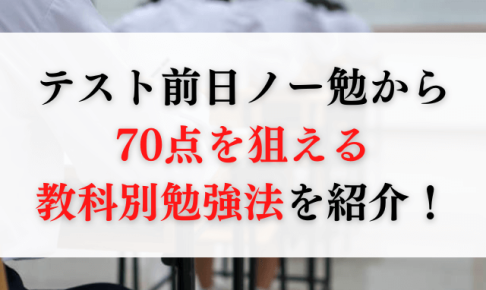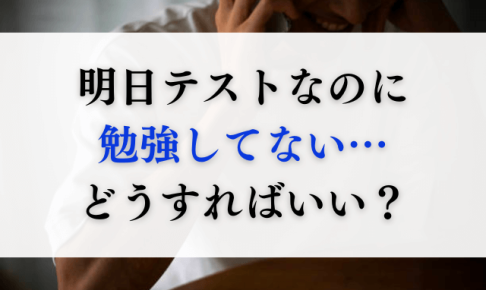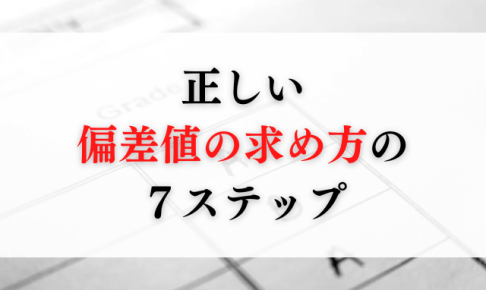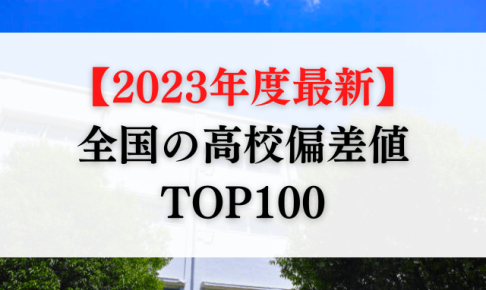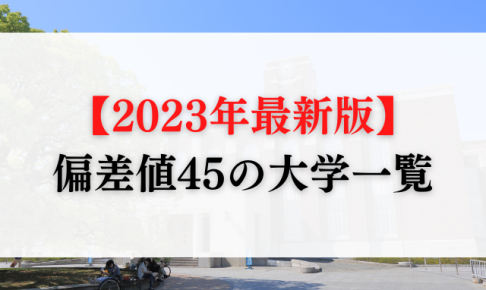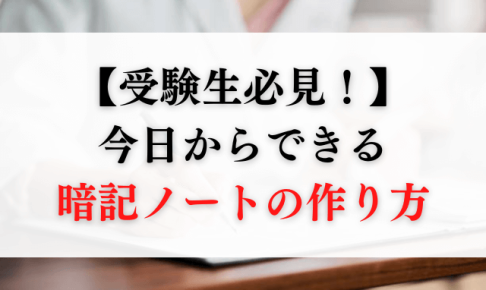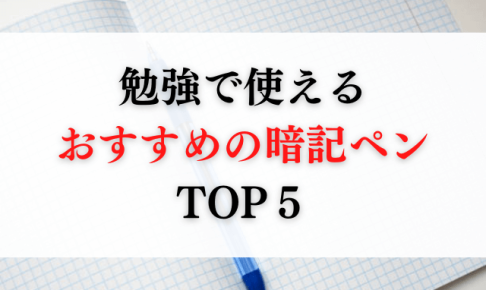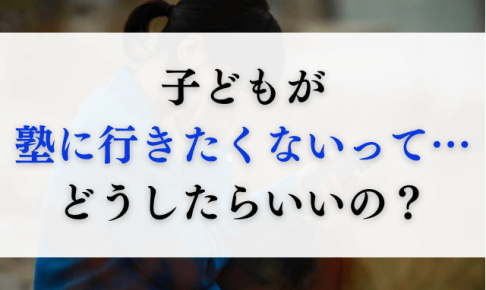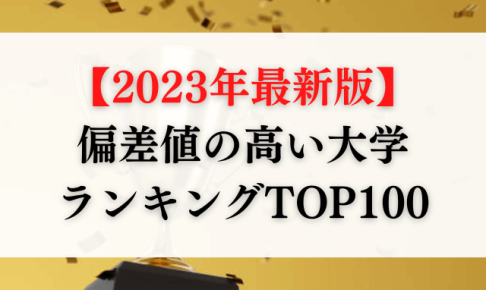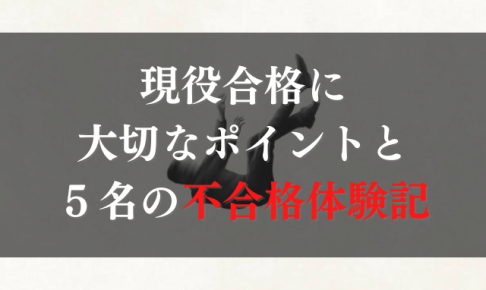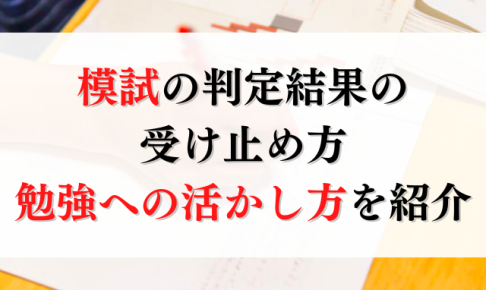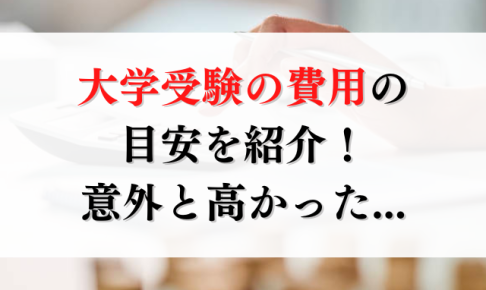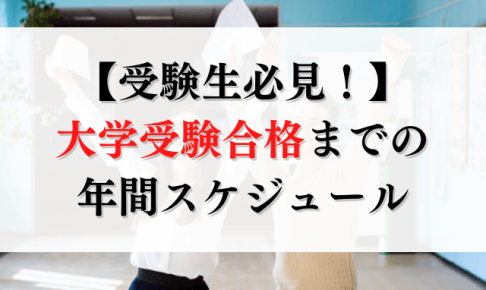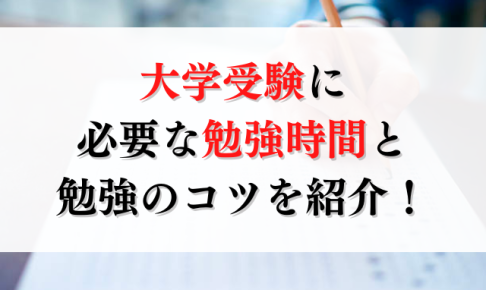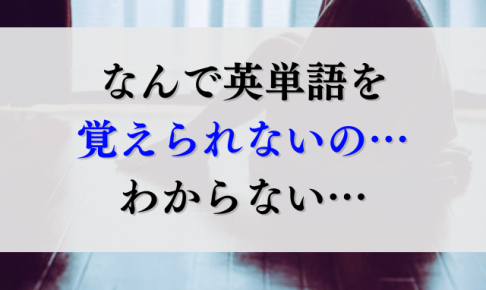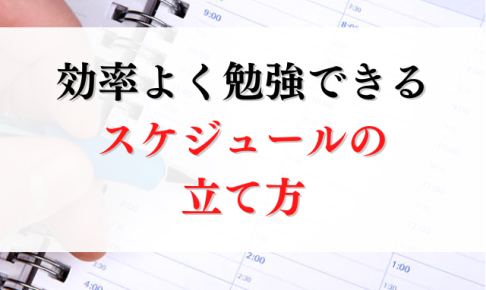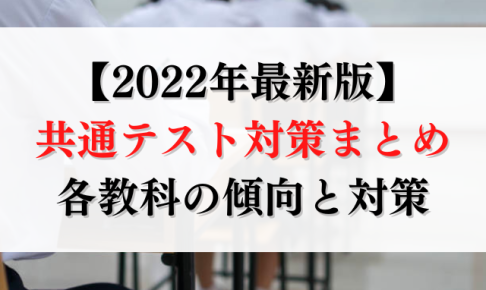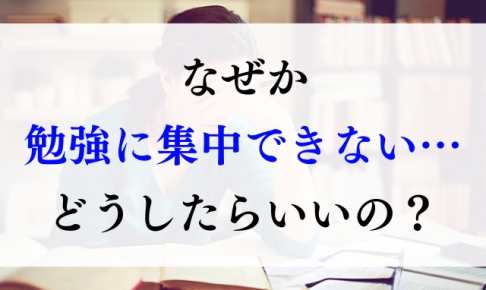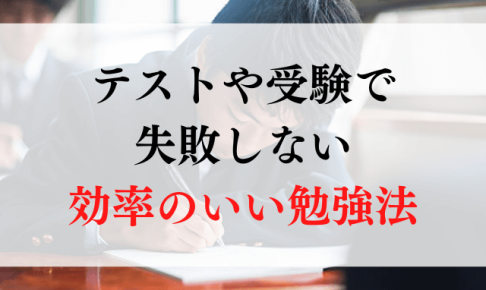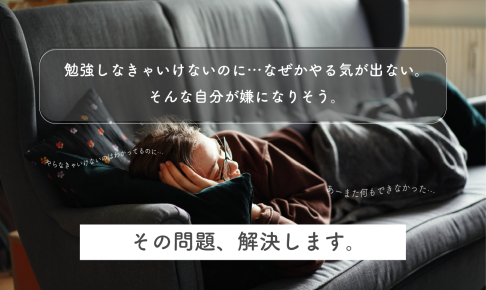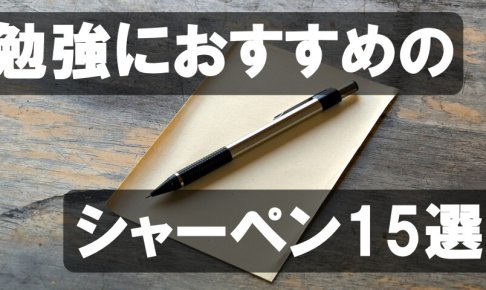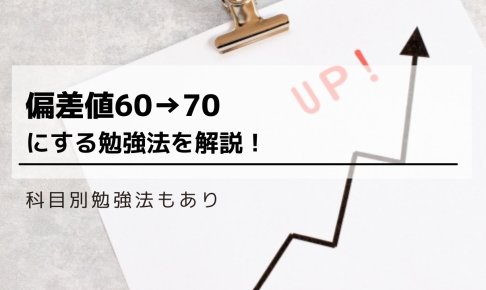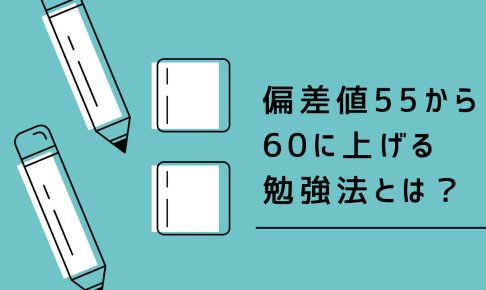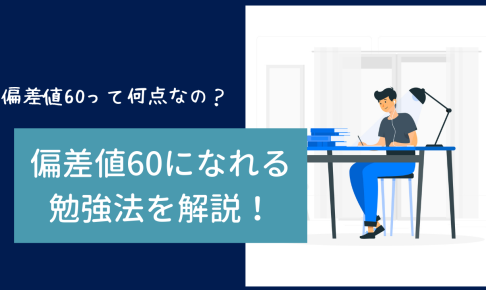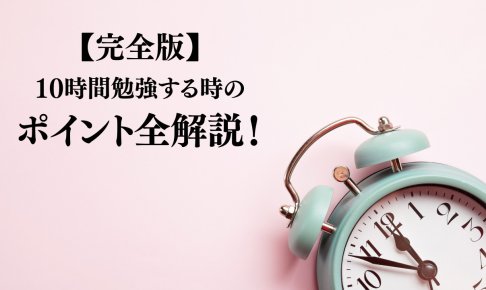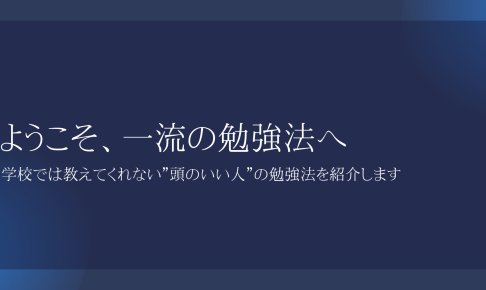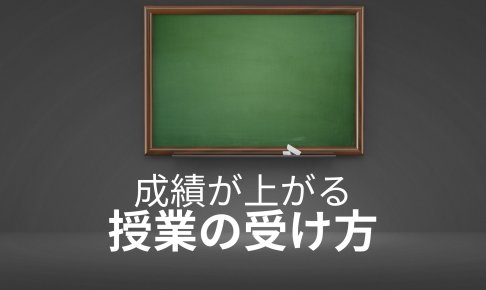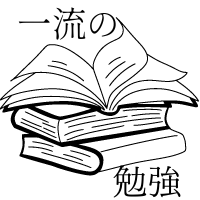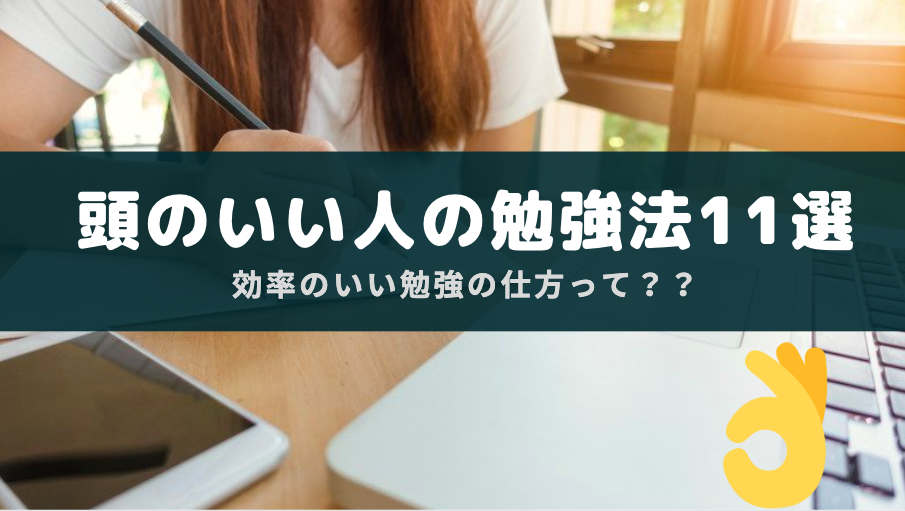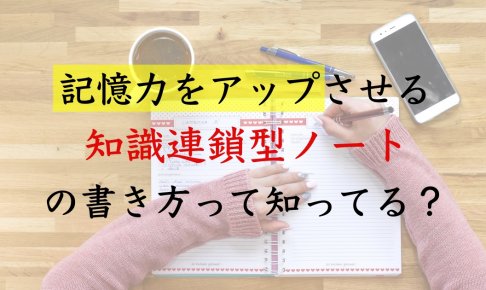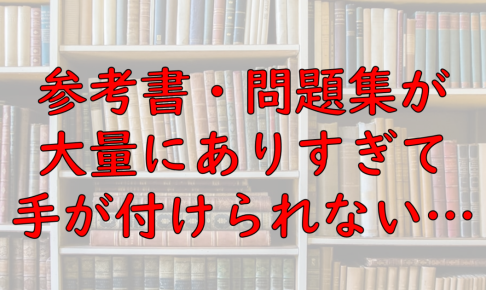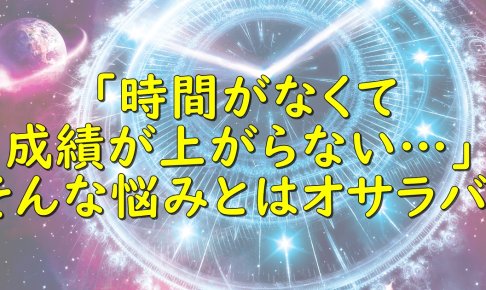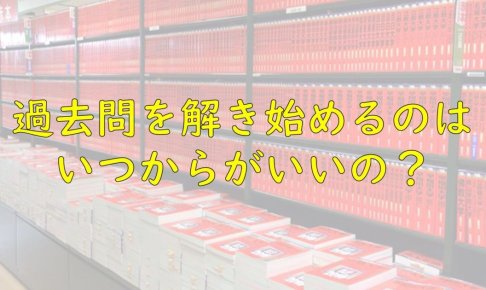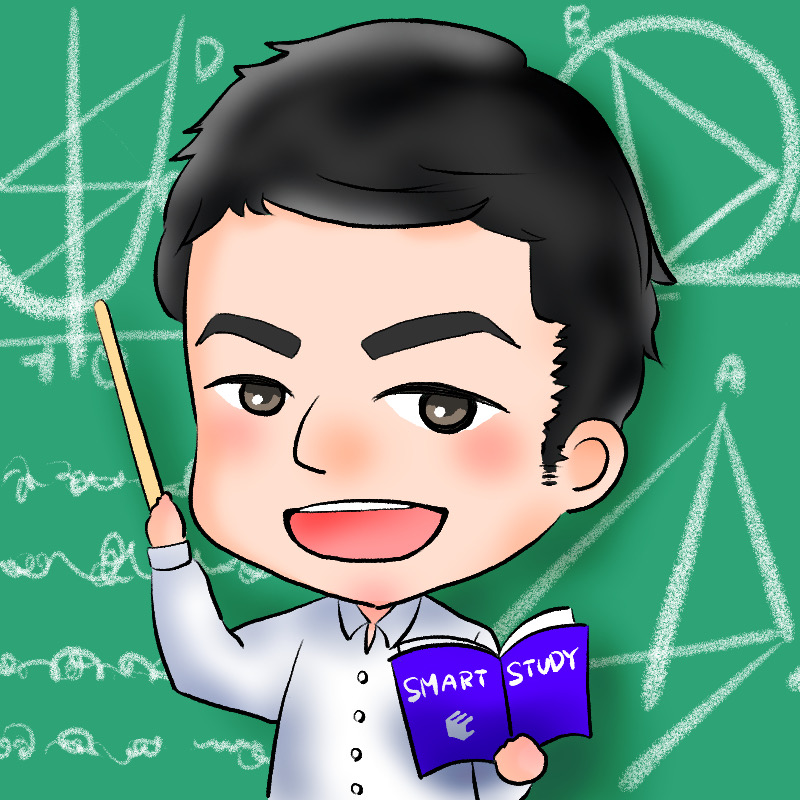
| 京大、阪大、早稲田大、筑波大などトップ大学に合格者を輩出する偏差値UP学習術とは? |
|---|
 |
|
【今だけ5,000円→無料!】 無料で読める電子書籍「偏差値UP学習術25選」 ・苦手科目を克服しようとすると成績が下がる理由 ・勉強しても成績が伸びなくなるブレーキの存在 ・1日5分で効率の良い勉強を習慣にする方法 などなど。 受験生であれば、ついつい気になる受験の仕組みを、プロが解説付きの電子書籍で徹底解説! 受講料は無料で受けられるので、受験生にも話題に! 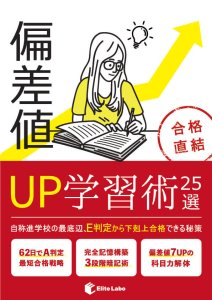
京大、阪大、早稲田大、筑波大などトップ大学に合格者を輩出する受験コーチのメソットを無料の電子書籍を、今すぐ無料で読むことができます! 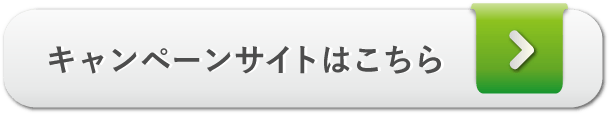
※無料ですぐに読むことができます。 |
・頭のいい人の勉強法が知りたい!!
・勉強した内容が頭に入る勉強法って?
・効率のいい勉強の仕方って?
効率的に勉強したいと思っている人の疑問に答えます。
今回の記事では効率のいい勉強法と悪い勉強法を両方、合計11個解説します。
効率が悪い勉強法も、この記事では一緒に紹介しています。
ついつい、やってしまっている勉強法も1つはあるはずなのでじっくり見てみてください!
どれだけ勉強時間が増えても、効率が悪い勉強法をしてしまっていると、成績の伸びが少なくなってしまいます。

| 京大、阪大、早稲田大、筑波大などトップ大学に合格者を輩出する偏差値UP学習術とは? |
|---|
 |
|
【今だけ5,000円→無料!】 無料で読める電子書籍「偏差値UP学習術25選」 ・苦手科目を克服しようとすると成績が下がる理由 ・勉強しても成績が伸びなくなるブレーキの存在 ・1日5分で効率の良い勉強を習慣にする方法 などなど。 受験生であれば、ついつい気になる受験の仕組みを、プロが解説付きの電子書籍で徹底解説! 受講料は無料で受けられるので、受験生にも話題に! 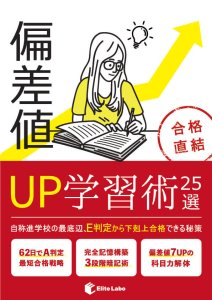
京大、阪大、早稲田大、筑波大などトップ大学に合格者を輩出する受験コーチのメソットを無料の電子書籍を、今すぐ無料で読むことができます! 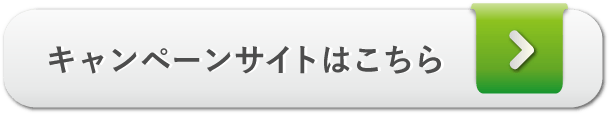
※無料ですぐに読むことができます。 |
勉強しないのに頭がいい人は
効率的な勉強を知っている

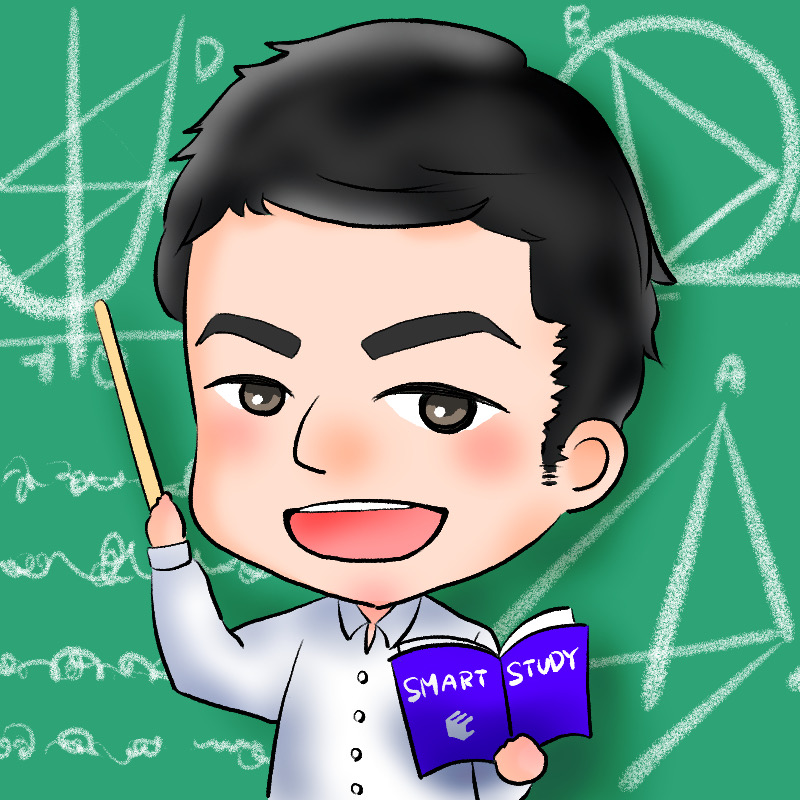
クラスに1人くらい、なんであいつ勉強できるんだろう?という人がいますよね。
勉強しているような様子が見えないけど、定期テストや模試でも良い点数を取ってくる人がいると思います。
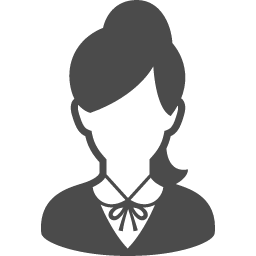
こんな風に、思ったことがある人もいるかもしれません。
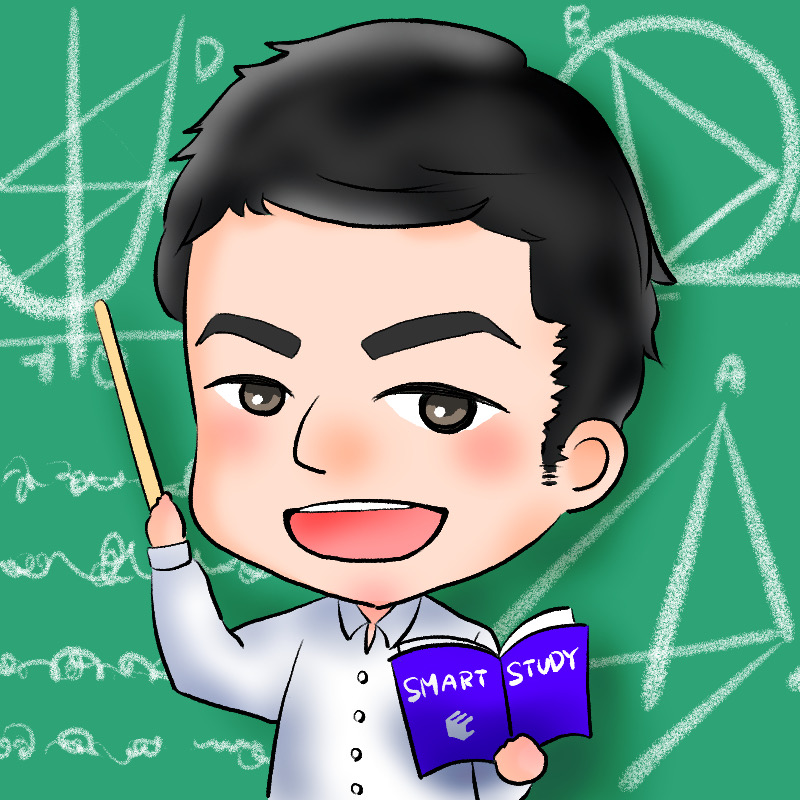
勉強していなそうに見える優秀な生徒も、勉強をしていないわけではありません。

成績を上げるために絶対必要な2つのこと

成績を上げるためには『高い勉強の質』と『長い勉強時間』が必要です。
勉強時間がどれだけ長くても、勉強の質が低かったら成績はなかなか伸びません。
同様に、勉強の質が高くても、勉強時間が短かったら成績はなかなか伸びません。
勉強の質と勉強時間のどちらか一方でも欠けてしまうと、成績は伸びなくなります。
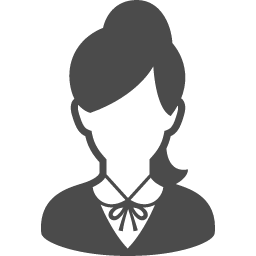
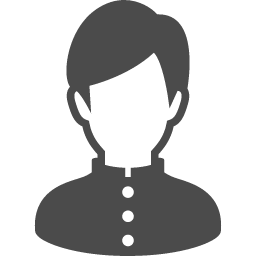
こんな風に勉強時間を確保しているのに、成績が上がらない人はいると思います。
こういった生徒は、勉強時間は長いけど、勉強の質が高くないのです。
言い換えるならば、成績が伸びない生徒は、『質が高い勉強法』を知らないまま、ただ勉強時間を増やしている状態です。
一方で、頭がいい生徒は、『質が高い勉強法』を知っていて、勉強をすればするだけ成績が伸びる状態です。
もし、あなたが、質が高い勉強をして、成績を上げたいならば、今回の記事最後までじっくり読んでください!
頭がいい人がどんな風に、質が高い効率的な勉強をしているのかを、徹底解説していきます。
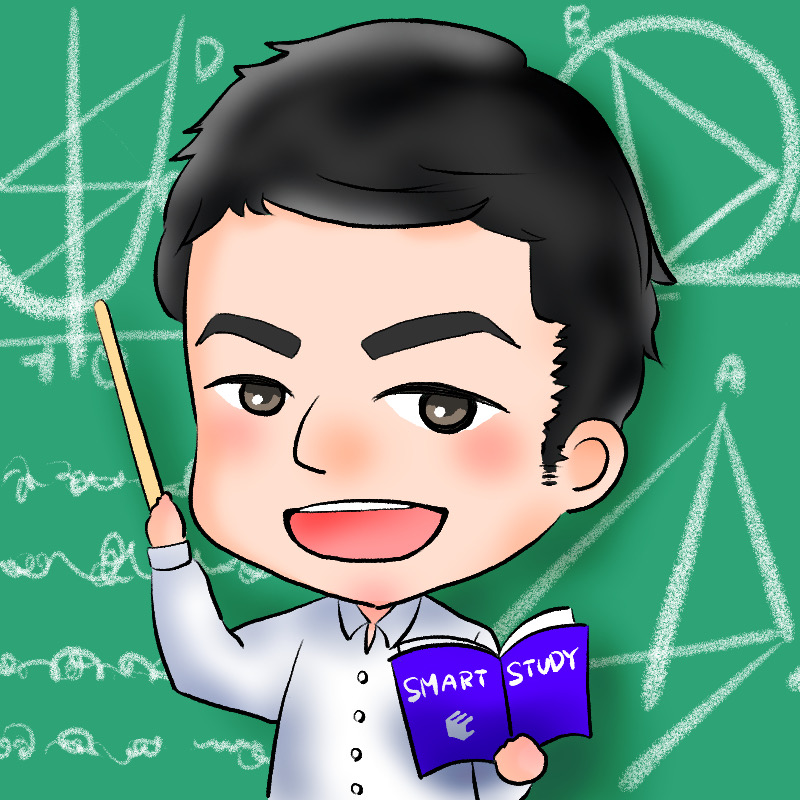

頭のいい人がしている
効率のいい勉強法11選

頭のいい人がしている効率のいい勉強法はこれらです。
- 暗記モノはスケジュールを組んでとりくむ
- 暗記モノは声に出して覚える
- まとめノートを作らない
- 使う参考書は各科目数冊だけ
- 合格から逆算した勉強計画がある
- 勉強時間にとらわれていない
- 勉強中に適度に休憩のタイミングを作る
- ONとOFFのメリハリがある
- 勉強効率化のツールをつかっている
- 情報収拾をしっかり行なっている
- 時間帯で勉強する科目を分けている
1つずつ、効率の悪い勉強法と対比しながら解説していきます。
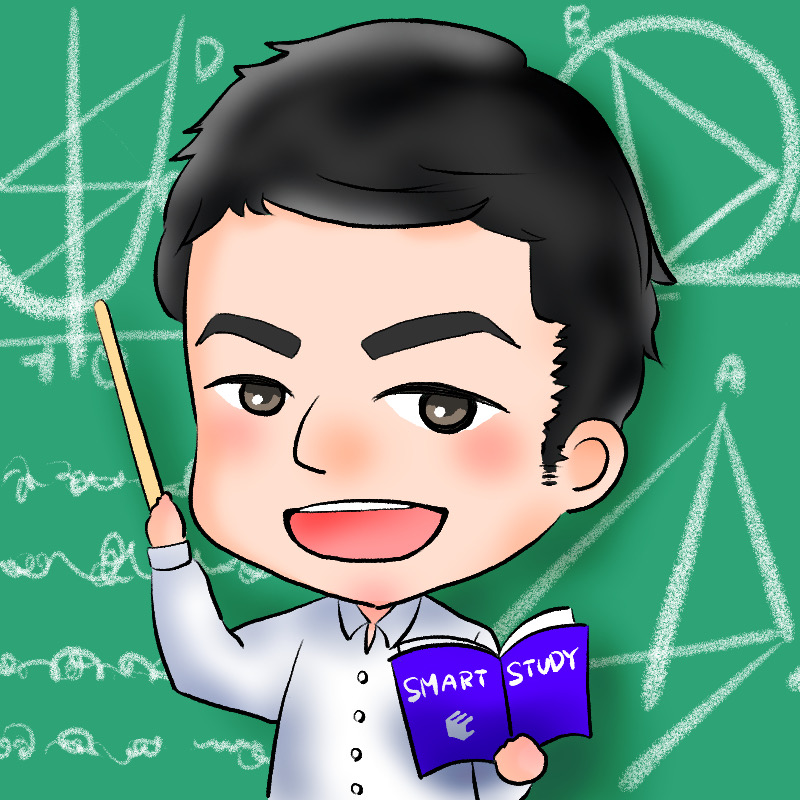
暗記モノは何回も反復して覚える

効率が良い勉強法→何回も反復して暗記をする
効率が悪い勉強法→短期間で数回しか反復しない
勉強の効率がいい人は英単語にしても、古文単語にしても、必ず1日のスケジュールにまで落とし込みます。
そして、単語帳など暗記モノを勉強する時に、数週間〜数ヶ月かけて何周も反復して定着させていきます。
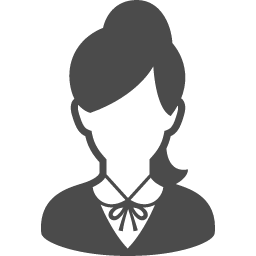
こんな風に、計画を立てて、決めた期間内に、何回も反復して暗記をしていきます。
計画的にコツコツ繰り返し反復して、長期記憶にしていきます。
一方、効率の悪い勉強をしている人は暗記モノを数日で終わらせようとします。
1000個ある単語帳を3日や1週間で終わらせようとするのです。
当然ですが1日に100も300も単語を覚えても、次の日には半分以上忘れてしまっています。計画性がないので遅れを取り戻そうとまとめてやろうとするのですが、当然効果は薄いということです。
3日とか1週間だと、単語を繰り返しみる回数が少なくなってしまいます。
暗記モノは声に出しておぼえる
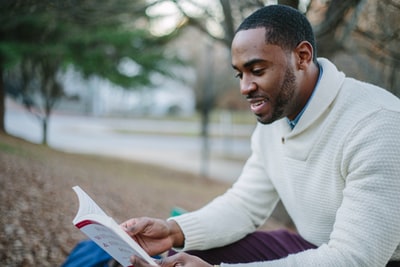
効率が良い勉強法→声に出して暗記をする
効率が悪い勉強法→紙に何度も書き出して暗記する
頭がいい人は暗記モノは音読する人が多いです。
音読する効果は
- 目と耳で覚えられる
- 短い時間で覚えられる
です。
とくにテスト前日などは音読してサクッと暗記モノを一夜漬けで終わらせる能力が高いです。
黙読で暗記モノを見るときは、視覚しか使いませんが、音読をすることで、聴覚も刺激します。
五感を刺激することで、暗記の効率は上がっていきます。
その一方、効率の悪い人は暗記することを紙に何度も書きます。
- agree・・・同意する
- agree・・・同意する
- agree・・・同意する
こんな感じです。
もし今記事を読んでいるあなたがこんな勉強をしているなら今すぐやめましょう。
僕の体感値では効率の悪い勉強をしている人の9割はこの勉強をしています。
書いて覚えるのは、時間もかかるし、疲れるし、非効率です!
まとめノートを作らない

効率が良い勉強法→ノートまとめを基本的にせず、参考書を使う
効率が悪い勉強法→綺麗なノートまとめをする
効率のいい人はまとめノートをあまり作りません。基本的にまとめノートは自己満足にしかすぎません。
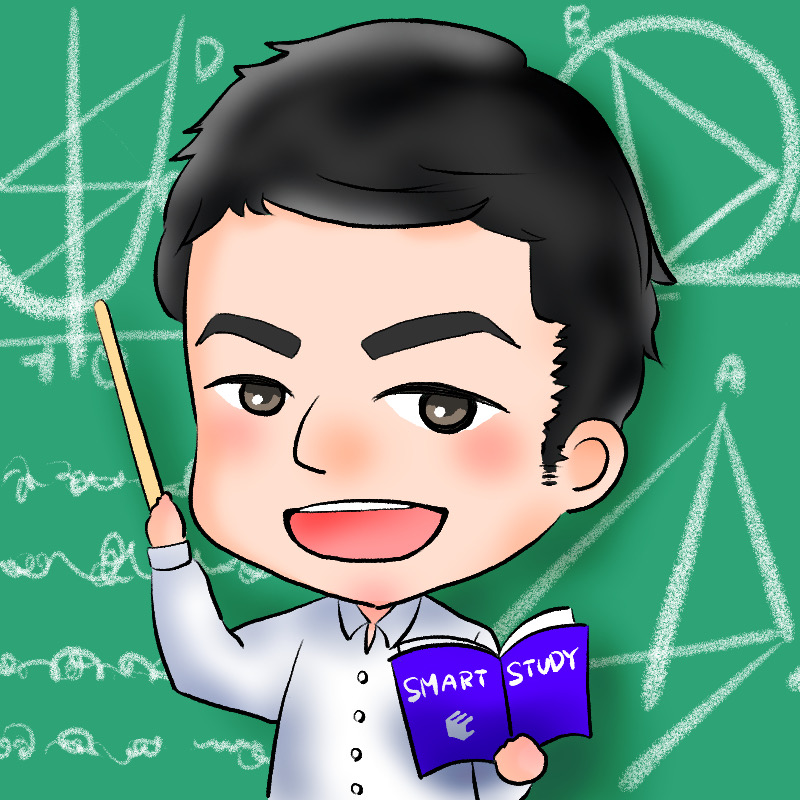
まとめノートに似たものは市販の参考書にあるケースがほとんどなので、頭のいい人は参考書を読んですませます。
まとめノートが綺麗に出来上がったら、達成感はあるかもしれません。
しかし、時間をかけた割には、定着はほとんどしていないことが多いです。
まとめている時は、教科書などの情報を、ノートに移しているだけの『作業』になってしまう可能性が高いです。
しかし、効率の悪い人はまとめノートを作成したがります。
テスト勉強のたびにまとめノートを作る人は多いですよね。英単語を紙に何度も書くような人はまとめノートも作りがちです。
そういう人たちは結論、「書いたら覚えられる」と考えているのでしょう。しかし、当然これは違います。
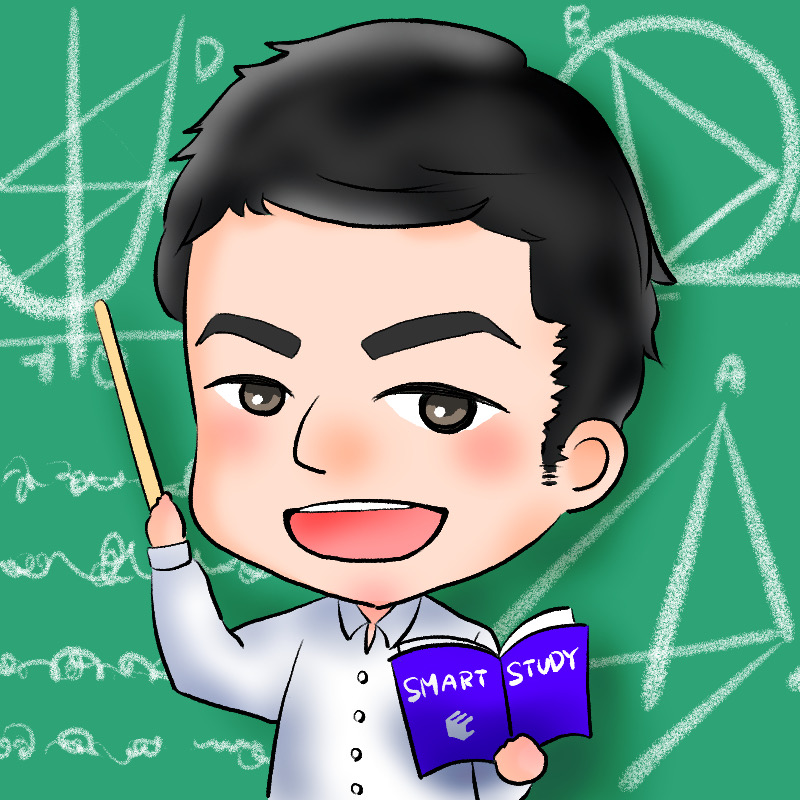
脳死で書いたりまとめたりするだけで覚えれるなら、皆そうしています。頭のいい人は参考書をまとめノートの代わりに使っていることが多いです。
使う参考書は各科目数冊だけ

効率が良い勉強法→各科目数冊に絞る
効率が悪い勉強法→色々な参考書に手を出す
頭のいい人は使う参考書が各科目決まって数冊なケースが多いです。
色々な参考書に手をだしてちゃんと理解できないよりも、1つの参考書をじっくり時間かけて勉強した方が効果的なことを理解しているのでしょう。
各科目、決めた参考書の数冊を徹底的に使い込んで、定着させていきます。
反対に効率の悪い人はやたら参考書を買って、全部をやろうとします。
しかし、受験業界に数ある参考書の全てをやるのは普通に考えて不可能です。
すべての参考書が中途半端な出来になってしまい、かえって1つの参考書をやったときよりも効果は低くなってしまう可能性もあります。
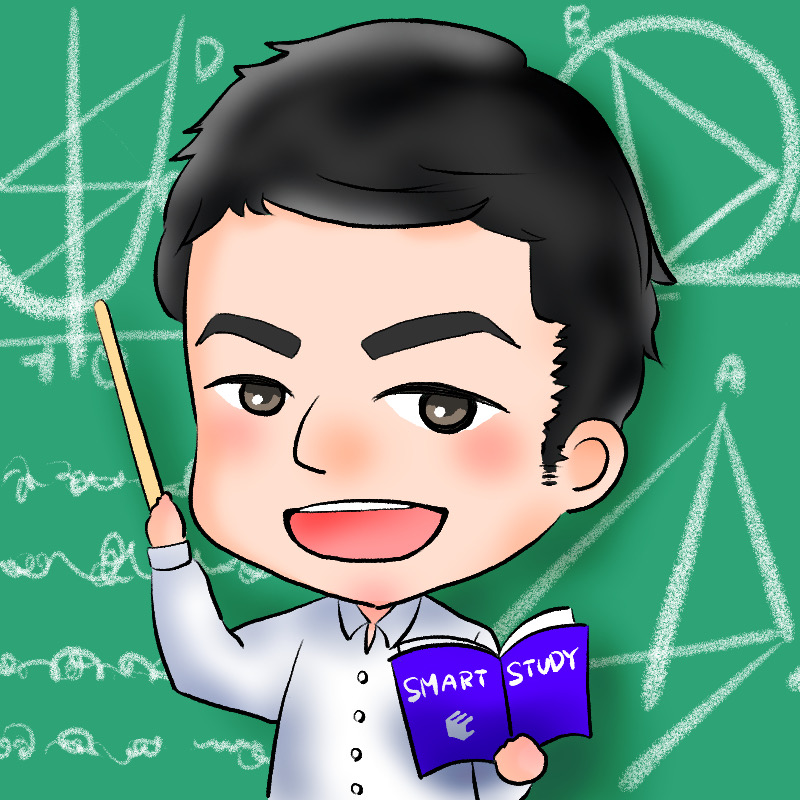
いくら沢山の参考書を持っていて、詳しくなっていても、参考書の内容が定着していなかったら意味がありません。
合格から逆算した勉強計画がある

効率が良い勉強法→合格から逆算した計画を作って勉強する
効率が悪い勉強法→計画を立てず、その日の気分で勉強する
これは効率のいい人と悪い人の決定的な違いです。
効率のいい人は合格から逆算した勉強計画を1日単位で作成していることがおおいです。
毎日勉強する前に「今日はなんの勉強をしようか???」と考える時間が、勉強計画を作ることでなくなるので、目の前の勉強に集中することができます。
合格をゴールとして、逆算して今やるべきことを明確にしています。
その一方、効率の悪い人は毎日の勉強計画を以下のような感じで作っていきます。
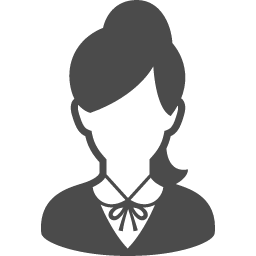
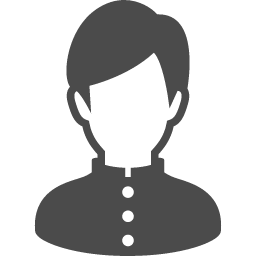
こんな感じで、合格から逆算した計画を立てるのではなくて、その日の気分などで勉強する内容を変えていきます。
このようにだらだら勉強している人は当然ですが、なかなか成績も伸びません。
戦略のない勉強はやらない方がマシです。
勉強時間にとらわれていない

効率が良い勉強法→勉強時間だけに囚われない。勉強の質✖️勉強時間を最大化させる
効率が悪い勉強法→勉強時間にこだわる
最初にもはなしましたが、頭のいい人は成績アップに必要なことが
『高い勉強の質』と『長い勉強時間』
ということを理解しています。なので、何時間勉強したかということに重きを置いていない人が多いです。
それよりも彼らは勉強の質と時間の掛け算を大事にしています。
具体的に数字で話すとこんな感じ。
- 質(0.8)✖️勉強時間(1.2)=0.96
- 質(1)✖️勉強時間(1)=1
- 質(1.2)✖️勉強時間(0.8)=0.96
- 勉強の質は低いけど、長時間勉強している
- 勉強の質は高いけど、勉強時間は少ない
というよりも、質も時間も一定をキープできる人の方が成績はいいのです。
一方、これを理解していない人の多くは
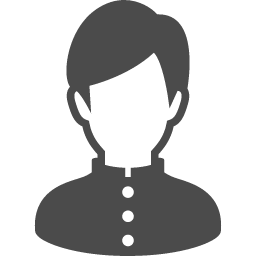
こんな風に、勉強時間の増加=成績アップと勘違いしています。
勉強時間を記録するアプリを利用している人は多いですが、時間を記録することが目的になっていませんか?
今ギクッとした人、要注意です。
勉強時間だけに重きを置かずに、勉強の質と勉強時間の掛け算を意識しましょう!
勉強中に適度に休憩するタイミングを作っている

効率が良い勉強法→計画の中に休憩を入れて、こまめに休憩をする
効率が悪い勉強法→休憩をしないで、長時間ぶっ通しで勉強する
効率的な勉強をする人は
- 今日は12時〜18時までぶっ通しで勉強するぞ!!!
というようなことは絶対に考えていません。それよりも、
- 今日は12:00~14:00までやって14:30まで休憩
- 14:30~16:00までやって17:00まで休憩
- 最後に18:00まで1時間勉強しよう
というように勉強スケジュールの中に休憩を組み込んでいるケースが多いです。
彼らは人間が効率よく集中して勉強できる時間が長くない、ということを理解しているのです。
一説では、45分勉強して15分休憩するのが効率的だとも言われています。
(http://www.asahi.com/ad/15minutes/article_02.html)
なので皆さんが思うよりも、人間の集中力はないのです。
効率が悪い生徒ほど、休憩時間を取らずに長時間ぶっ通しで勉強をします。
集中できていない勉強を長時間続けていても、質がどんどん下がっていくだけです。
ONとOFFのメリハリがある

効率が良い勉強法→勉強する時とリラックスする時のメリハリがある
効率が悪い勉強法→メリハリがなく、ダラダラと勉強をする
ONとOFF、つまり勉強するときとしないときのメリハリがしっかりしている人は、頭のいい人が多いです。
効率のいい人は勉強しないと決めたら、全く勉強せずにリラックスします。その一方でやるぞと決めたら、一気に集中して勉強できるのです。
しかし効率の悪い人は
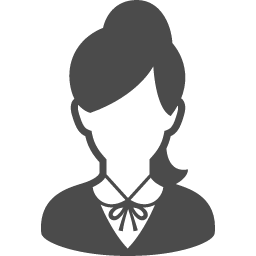
という気持ちのせいで、ダラダラ勉強してしまっている人が多いです。
その結果、勉強時間は長いものの集中力もなければストレスも増えていくばかりです。
勉強効率化のツールをつかっている

効率が良い勉強法→勉強効率化のツールを使う
効率が悪い勉強法→特にツールを使わない
効率的な頭のいい人は勉強効率化のツール(アプリなど)を利用している人が多いです。
例えば勉強時間を記録するアプリなら、スタディープラスがありますが、こうした勉強を管理するアプリを使って
- 勉強時間を見えるようにする
- 科目別の自分の勉強時間の偏りを知る
といったことを実践しています。
今、この記事を読んでいる高校生のあなたはスマホを持っていることでしょう。
それなのにこうした効率化のためのツールを使っていないのは、現状情報不足と言わざるをえません。
情報収拾をしっかり行なっている

効率が良い勉強法→情報収集して、必要のないところは勉強しない
効率が悪い勉強法→情報収集しないため情報が少なく、必要のない範囲まで勉強をする
- A先生のテストはよく積分の応用問題が出るらしい
- B大学の数学の試験は微分がよく出るらしい
- 自分の得意科目的に私立はC大学を受験するのが良さそうだ
- D大学の日本史は江戸時代は出ないらしい
頭のいい人はこのようにテスト・受験の情報収拾をしっかりやっていることが多いです。
このような情報を入手しておけば、自分の勉強すべき科目・分野が簡単にわかります。D大学の勉強として江戸時代はすっ飛ばしてOKです。
その一方で効率の悪い人は情報収拾をしなかった結果、D大学の日本史の勉強で江戸時代の勉強をしてしまいます。
これは情報収拾の問題でもありますし、また合格からの逆算ができていない証拠でもあります。
自分の志望校などの情報を集めて、力を入れるところと、力を入れなくても良い範囲を明確にしましょう!
時間帯で勉強する科目を分けている

効率が良い勉強法→時間帯ごとに勉強する科目を分ける
効率が悪い勉強法→時間帯ごとに科目を分けず、やる科目の時間帯はその日の気分
効率のいい人は時間帯で勉強する科目を決めています。
例えば、
- 朝は頭が冴えるから演習問題をとく
- 寝る前は頭が働かないから暗記モノを覚える
というように自分の頭の集中度によって、やることを分けていたりします。
頭がいい人は自分の身体を理解して、いつ、なんの科目を勉強するのが効率よく集中できるのかを理解できているケースが多いです。

頭のいい人の1日の勉強スケジュール

効率が良い勉強法→朝の時間を有効活用している
効率が悪い勉強法→朝の時間をなんとなく使う
頭のいい人は1日をどのように過ごしているのでしょうか。
僕の経験則から彼らは朝の時間を有効活用している人が多いです。
学校のある日なら↓
- 6:00起床&勉強&朝ごはん
- 8:00登校
- 18:00帰宅(部活あり)
- 18:30食事
- 19:00高校の宿題
- 20:30お風呂&リラックス
- 21:30勉強
- 23:00勉強終了
- 23:30就寝
これで学校以外で1日4時間程度は勉強できます。
休日なら↓
- 8:00起床&朝ごはん
- 8:30勉強
- 10:00休憩
- 10:30勉強
- 12:00昼ご飯&リラックス
- 14:00勉強
- 17:00休憩&ご飯
- 19:00勉強
- 21:00お風呂&リラックス
- 23:30就寝
これで休日は1日8時間は勉強した計算です。
もちろん最初は勉強の質を高くしていきたいので、これを読んだ今から平日1日4時間も勉強することはしなくてOKです。
しかしもしあなたが受験でいい大学を狙うなら、効率も高めつつ徐々に勉強時間も伸ばしていきましょう。
朝は、頭がスッキリしていて、集中力も高い時間なので、朝の時間帯を有効活用していきましょう!

最初は手を動かすことが大切
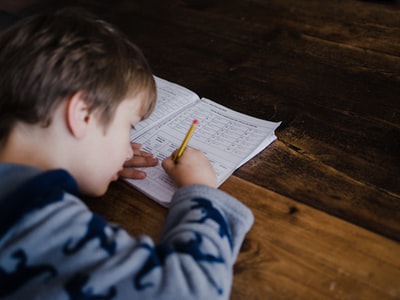
ここまで効率のいい勉強法を紹介してきましたが、今回紹介した方法のうち、あなたが
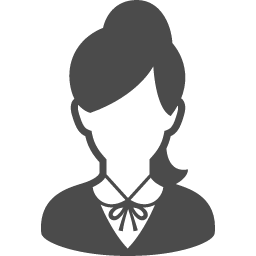
と思った勉強法があれば早速実践してみてください。
この記事を読んでいるあなたは、何か今までの勉強法と変えたいという気持ちが強いはずです。
食わず嫌いをせずに、まずはやってみるということをおすすめします!
実際に頭の中で、何をするのが良いのかがわかっていても、やってみないことには、何も始まりません。
今回は頭のいい人の勉強法をテーマに解説してきました。
何度か紹介しましたが
- 高い勉強の質✖️長い勉強時間
これが成績アップの方法です。
頭のいい人が実践している効率的な勉強法をあなたも使ってみて、まずは勉強の質を高めていきましょう!
その上で徐々に勉強時間も増やしていきましょう!
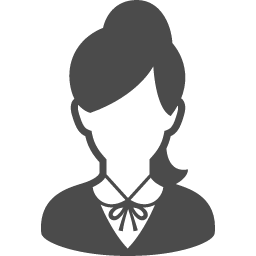
あなたに合った勉強法を診断します!
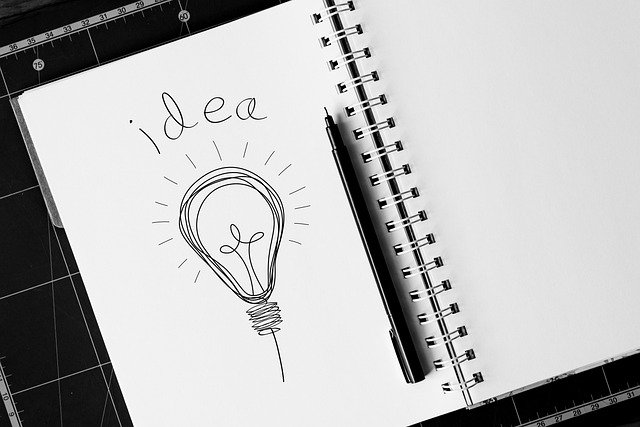
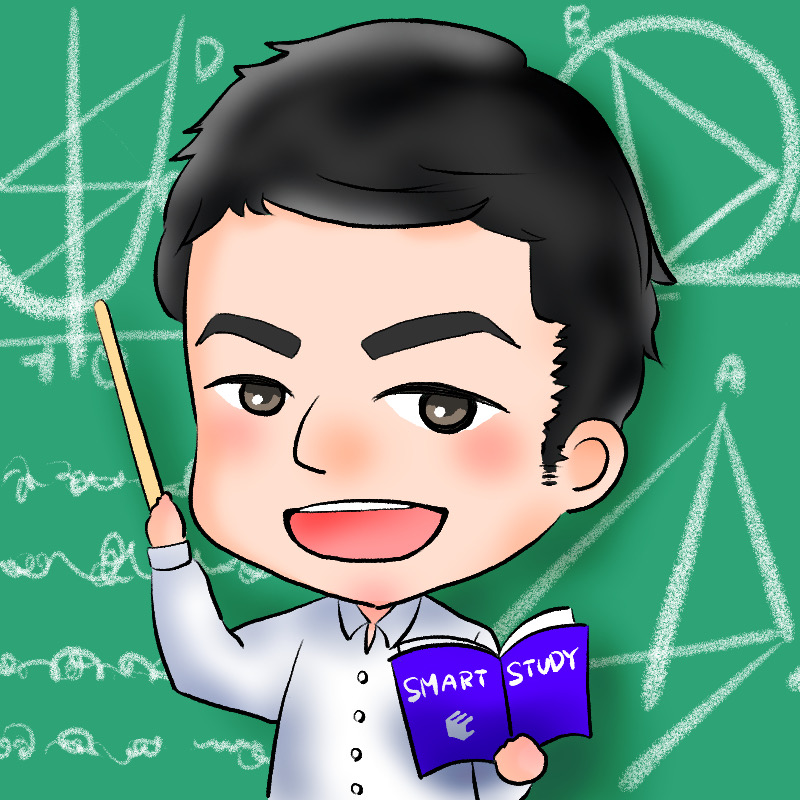
今回の記事では、 『頭がいい人』がどんな勉強法で勉強しているのかを、合計11個紹介 してきました!
実際に、これまであなたがやってこなかったような勉強法も沢山合ったはずです。
実際に、ここで紹介した勉強法も試してみてほしいのですが、 高い勉強の質✖️長い勉強時間が、頭良くなるためにはとても重要に なってきます。
勉強時間をいくら増やしても、勉強の質が伴っていないと、あなたの成績は全然上がっていきません。
あなたに合った勉強法で、勉強をいくら長時間やっていても成績は伸びません!
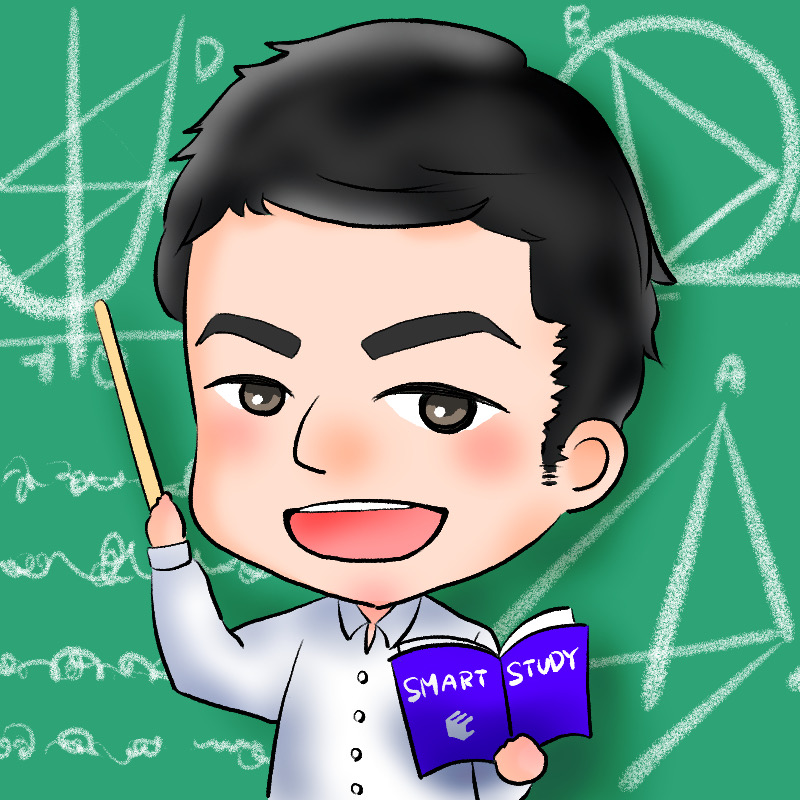
以下の記事では、『あなたに合った勉強法』をたったの12個の質問で診断していきます!
『あなたに合った勉強法』を見つけて、確実に成績をあげていってください!!
| 京大、阪大、早稲田大、筑波大などトップ大学に合格者を輩出する偏差値UP学習術とは? |
|---|
 |
|
【今だけ5,000円→無料!】 無料で読める電子書籍「偏差値UP学習術25選」 ・苦手科目を克服しようとすると成績が下がる理由 ・勉強しても成績が伸びなくなるブレーキの存在 ・1日5分で効率の良い勉強を習慣にする方法 などなど。 受験生であれば、ついつい気になる受験の仕組みを、プロが解説付きの電子書籍で徹底解説! 受講料は無料で受けられるので、受験生にも話題に! 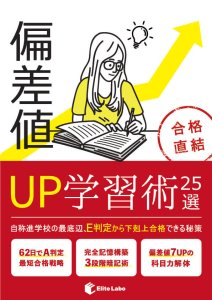
京大、阪大、早稲田大、筑波大などトップ大学に合格者を輩出する受験コーチのメソットを無料の電子書籍を、今すぐ無料で読むことができます! 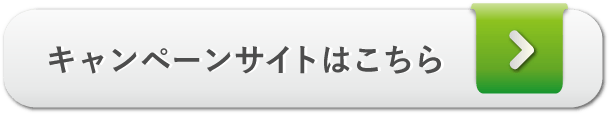
※無料ですぐに読むことができます。 |